カリキュラム
CURRICULUM
カリキュラム内容
1年次
言語聴覚士として基礎的な科目を学びながら、豊かな人間性と広い教養を養います。
| 基礎科目 |
|
|---|---|
| 専門基礎科目 |
|
| 専門科目 |
|
| 臨床実習 |
|
2年次
専門的な知識・技術を深め言語聴覚士としての素地を作ります。
| 基礎科目 |
|
|---|---|
| 専門基礎科目 |
|
| 専門科目 |
|
| 臨床実習 |
|
3年次
障がいに応じた評価や訓練方法を学び治療計画の立案や結果の予想・評価を実現できることを目指します。
| 基礎科目 |
|
|---|---|
| 専門基礎科目 |
|
| 専門科目 |
|
| 臨床実習 |
|
4年次
専門職として総合的な学習を行い、4年間の総仕上げをします。
| 基礎科目 |
|
|---|---|
| 専門基礎科目 |
|
| 専門科目 |
|
| 臨床実習 |
|
履修モデル
言語聴覚学専攻のカリキュラムについて、4年間の履修の流れをまとめた、モデル表です。
カリキュラムの特長
高い自律性、豊かな人間性、医療従事者としての人格を獲得するため、高度の専門性を踏まえつつ、その専門性の中に閉じこもることなく、人道的な素養の育成を目指します。
授業ピックアップ!
-
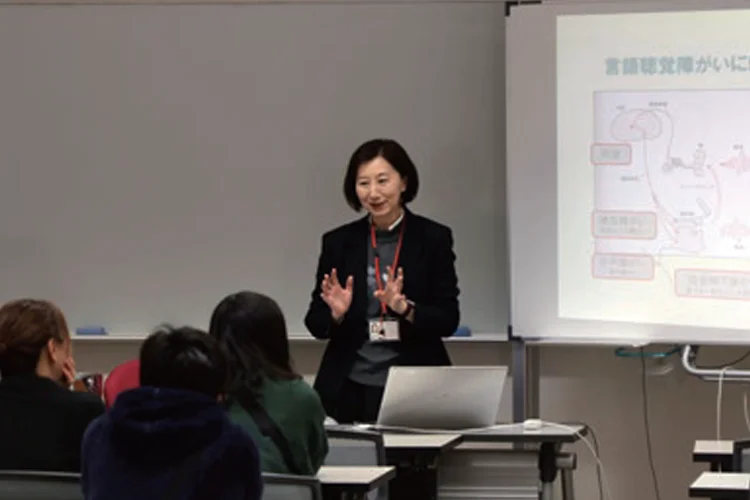
言語聴覚障害学総論Ⅱ
「ことば」や「聞こえ」などの障がいにはどんな種類があるのか、どうやって起こるのかを学びます。また、うまく食べたり飲み込んだりできなくなる「摂食・嚥下障がい」についても、体の仕組み(解剖学・生理学)からその原因を理解し、どのようなリハビリができるのかを学びます。
-

聴覚検査法
耳の聞こえの状態を調べる「聴覚検査」について、どのような方法があるのかを体系的に学びます。実際に使われる聴覚検査機器や騒音計などの使い方や、検査結果の読み取り方、その意味なども、演習を通してしっかり身につけていきます。
-

失語・高次脳機能障害学Ⅰ
「失語症」という、言葉をうまく話せなくなったり理解できなくなったりする脳の障がいについて学びます。脳のしくみ(どの部分がどんな役割をしているか)や、失語症がどのようにして起こるのか、どんな特徴があるのかを学びます。実際の患者さんの声や動画、脳の画像などを使って理解を深めていきます。
-

言語発達障害学Ⅱ
子どものコミュニケーションに関わるさまざまな障がいについて学びます。そして、それぞれの障がいにおいてどのように言葉の発達に影響が出るのか、その評価や診断の方法、子どもに合わせた指導や訓練の方法について理解を深めます。
-

音声障害学
「声が出にくい」「息苦しさを感じる」などの音声障がいについて学びます。実際の声枯れの音を聞いて理解を深めたり、喉頭を手術で失った人が使う「電気式人工喉頭」による代わりの発声法も学びます。
-

摂食嚥下障害学
「食べる」「飲み込む」といった動作に関わる体のしくみ(口やのど、食道など)を学びます。摂食・嚥下機能を調べるための検査や、うまく食べられるようにするためのリハビリや食事の工夫の方法を、演習を交えて学びます。
-

言語聴覚学PBL
リハビリテーション(機能回復の支援)に関わるさまざまな出来事や実際の症例をテーマに、自分たちで問題を見つけ、必要な情報を集め、話し合いながら解決の方法を考えます。そして、自分の考えを他の人にわかりやすく伝える力を身につけていきます。
-

統合言語聴覚学(含演習)
4年間の学びの集大成として、これまでに身につけた知識や技術を振り返りながら、実践的にまとめていく科目です。4年間の学びを「現場で活かせる力」としてまとめ直し、社会に出る準備を整えます。